コンビニエンスストアやカフェに立ち寄ると、カフェオレやキャラメルマキアート、カフェモカ、さらにはホットチョコレートなど、多彩な飲み物が目に飛び込んできて、思わず心を奪われてしまうことが多いですよね。
レストランに入ってみると、シチューやグラタン、ケーキ、プリン、パンケーキといった魅力的な料理がたくさん並んでおり、これらの料理には牛乳が欠かせない基本的な材料として使用されていることがわかります。このように、牛乳は私たちの日常生活のさまざまな場面で広く利用されており、今や私たちにとって欠かせない存在となっています。
しかし、そんな牛乳が大人になった私たちの健康に対して、実は悪影響を与える可能性があることをご存じでしょうか?
小学校や中学校の給食では、毎日牛乳を飲むことが習慣として取り入れられており、牛乳はカルシウムが豊富で健康に良いと教えられてきたため、多くの人々が健康のために牛乳を毎日欠かさず飲んでいるのではないかと思われます。
そこで今回は、牛乳の意外な側面について詳しくご紹介し、その影響を考えていきたいと思います。
日本人と牛乳の歴史
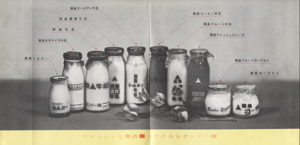
日本における乳製品の歴史は645年の飛鳥時代にさかのぼることができ、その起源は非常に古いものであると言えます。しかし、一般庶民の間に広まるようになったのは明治時代からのこととされています。
具体的には、1871年(明治4年)に天皇が「毎日2回牛乳を飲む」という記事が発表されたことがきっかけとなり、庶民の間でも牛乳を飲む習慣が浸透していきました。
さらに、1946年(昭和21年)には関東地方の21万人の児童に対して脱脂粉乳が給食として提供されるようになりました。
その後、現代に至るまで、日本人の牛乳消費量は昭和21年以降、おおよそ5倍に増加しました。このように、学校給食を通して牛乳が普及してからの75年余りの間に、その消費量が急激に増加した背景にはさまざまな要因が存在しています。
カルシウムが豊富って本当?
実は、牛乳を飲むことがかえって骨をもろくしてしまうという説も存在しています。
その理由は、日本人の牛乳消費量が一人当たり約20倍も増加しているにもかかわらず、骨粗しょう症が増加しているという現実です。
さらに、牛乳に含まれるたんぱく質を過剰に摂取すると、逆にカルシウムが体外に排泄されてしまうことも知られています。
このため、牛乳の過剰摂取は控えることが望ましいとされています。
アレルギー症状の悪化

さらに、牛乳は花粉症やアトピー、喘息といったアレルギー症状を悪化させる可能性もあることが指摘されています。
その主な原因はカゼインという牛乳に含まれるタンパク質です。実はカゼインは牛乳の約80%を占める重要な成分です。
日本人の約80%はカゼインを分解する酵素を持っておらず、未消化のまま腸に送られると腸粘膜が傷つき、炎症を引き起こすことがあります。
炎症が進行すると、腸粘膜のつながりが悪化し、腸に穴が開く状態になることもあり得ます。
その結果として、本来体内に入るべきでない物質が血液中に侵入し、免疫細胞がそれを排除しようとしてアレルギー反応を引き起こすことになってしまいます。
こうしたアレルギー反応は、花粉症や喘息、アトピーなどの症状を引き起こす原因となることがあります。
血管系の病気のリスクも

牛乳の摂取は、脳卒中や心筋梗塞、心不全、動脈硬化といった血管系の病気のリスクを高める可能性があるとされています。
その理由は、牛乳に含まれる飽和脂肪酸が中性脂肪やコレステロール値を上昇させるためです。
飽和脂肪酸を過剰に摂取すると、血液中に悪玉コレステロールが増加し、動脈硬化を引き起こす原因となる脂肪酸に変化します。
このような血管系の病気は、日常生活の習慣が重なり合って起こるものであり、もし牛乳を飲む習慣があるならば、思い切ってやめてみるのも一つの手かもしれません。
牛乳のメリット
牛乳は、準完全栄養食品と称されるほど、非常に優れた栄養バランスを持つ食品として広く知られています。
コップ一杯の牛乳に含まれる栄養素は以下の通りです:
・カルシウム35%
・ビタミンB2 25%
・ビタミンB12 25%
・たんぱく質 13%
さらに、筋トレや運動をした後、1時間以内に牛乳を飲むことで、糖質とたんぱく質が効率よく筋肉細胞に吸収され、筋肉量の増加に寄与することが期待できます。
また、牛乳に含まれるたんぱく質や糖質は、肝臓の機能を高めて血液量を増やす効果もあるとされています。
どんな牛乳なら飲んでいいの?

牛乳を選ぶ際には、生乳や生乳から作られたヨーグルト、バター、チーズなどを摂取するよう心がけると良いでしょう。
生乳と明記された商品を選ぶことがポイントです。
とはいえ、牛乳なしの生活では料理の選択肢が制限されることもあり、苦痛に感じる方もいるでしょう。
そのため、牛乳の代替品として、豆乳やオーツミルク、アーモンドミルクなどを試してみるのも良い選択肢となります。
豆乳やアーモンドミルクは、意外にも濃厚な飲み口を持つ製品も多く、ドリンクや料理に幅広く利用できることが魅力です。
なぜ大人は飲まない方がいいの?
大人にとっては、牛乳を常習的に飲まない方が良いとされています。
その理由は、成人になると体内の乳糖分解酵素がほとんど失われてしまい、牛乳を大量に摂取すると消化不良を引き起こす可能性があるからです。
カゼインは乳糖の一部でもあります。
本来、牛乳は牛の赤ちゃんが飲むためのものであり、成長するにつれて乳糖分解酵素は減少していきます。
日本人が牛乳を毎日飲むことが許されるのは、乳糖分解酵素が存在する乳幼児の時期までなのです。
したがって、牛乳を摂取するのは、運動をした後や時々カフェでカフェオレを楽しむ程度に留めるのが理想的です。
子供にも飲ませない方がいいの?

お子さんが成長してきたら、牛乳は少量にとどめるようにしましょう。
その理由は、前述の通り乳糖分解酵素が赤ちゃんの時よりも減少しているためです。
とはいえ、牛乳には成長期の子供にとって必要不可欠なカルシウムが豊富に含まれているため、他の食事とバランスよく組み合わせることが重要です。
目安としては、1日に牛乳1本(200ml)と100ml程度が適切とされます。
まとめ
牛乳を避けるべき理由をまとめてみました。
日常的に健康のために牛乳を習慣的に飲んでいる方は多いかもしれません。
普段あまり体を動かさない方にとっては、毎日の牛乳が体調不良の原因となる可能性も考えられます。
思い切って牛乳を飲むのをやめてみることで、体が軽く感じるかもしれません。
とはいえ、体に合う食材は人それぞれ異なるため、乳製品に限らず自分自身で試行錯誤しながら、一番自分に合った健康法を見つけていくことが大切です。




コメント