
皆さんは大豆ミートを試したことがありますか?
私自身、かなり前に乾燥タイプの大豆ミートを購入して食べた経験がありますが、その際の印象は正直なところ「肉もどき」や「人工肉」といったもので、本物の肉の風味や美味しさには到底及ばないと感じました。
そのため、その後は大豆ミートを購入することも、食べることも避けてきました。
しかし最近、偶然「ゼロミート」というハンバーグを発見し、食べてみたところ、本物の肉の食感に非常に近いことに驚かされました。
その味も、以前に試した大豆ミートよりも遥かに美味しく、私の印象を大きく変えるものでした。
脚光を浴びる大豆ミート

2020年頃から、ニュースやメディアで頻繁に耳にするようになった言葉にはSDGs(エスディージーズ)があります。
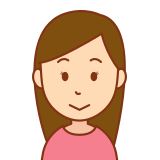
SDGsとは、「Sustainable Development Goals(サステナブル・デベロップメント・ゴール=持続可能な開発目標)」の略称であり、2030年を目指して持続可能でより良い世界を実現するための国際的な目標を指します。
貧困や飢餓の解消、気候変動など、21世紀において全世界が直面する課題を解決するために、17の目標が設定されています。
特に、食料需要の問題は非常に重要な課題であり、2021年の時点で、世界の10人に1人が飢餓に苦しんでいるという厳しい現実があります。
国連の予測によると、2050年には世界人口が97億人に達する見込みであり、このままでは世界の飢餓人口がさらに増加する恐れがあります。
このような深刻な食糧不足を解決する手段として期待されている食品は、「大豆ミート」のような代替肉なのです。
大豆ミートが注目される背景
世界中で人口が増加することに伴い、食肉の消費量が急増し続けることは、地球環境に対してさらなる負担をかけることは避けられません。
SDGsが目指す持続可能な世界を実現するためには、畜産業の縮小が不可欠であり、その背景には以下のような理由があります。
- 牛肉1kgの生産において必要な穀物は約7kg~11kgであり、その分を人間の食料に回すことで飢餓に苦しむ人々を減少させることが可能です。
- 地球温暖化の防止の観点からも、植物由来の代替肉を選ぶことで畜産から発生する温室効果ガスを減少させることができます。
- 畜産業は膨大な水を必要とするため、畜産が縮小されることで水不足の解消に繋がります。
- 畜産が縮小されることによって、家畜から人間に伝染する感染症のリスクを低減させることが期待されます。
広がる大豆ミートの市場

このような背景から、大豆ミートの認知度と需要は年々増加しています。
以前は、ナチュラルハウスなどの自然食品店でのみ取り扱われているイメージがありましたが、現在では一般のスーパーマーケットでも簡単に入手できるようになりました。
また、大手の外食チェーンでも大豆ミートを使用したメニューが増えており、手軽に楽しむことができるようになっています。
例えば、ロッテリアやモスバーガーなどのファストフード店では、「ソイパティ」を用いたハンバーガーが提供されており、ますます多くの人々が気軽に楽しむことができるようになっています。
健康志向が高い人に人気
「肉と比較してヘルシー」「環境にも健康にも良さそう」といったイメージから、大豆ミートを選ぶ人が増加しています。
大豆は「畑の肉」と称されるほどたんぱく質が豊富で、肉に比べて低脂肪・低コレステロールという特徴を持っています。
さらに、肉には含まれない食物繊維も豊富に含まれているため、健康を気にする人々の間で売上は増加傾向にあります。
参考URL:https://japan.cnet.com/article/35173196/
豊富な大豆ミートのバリエーション
現在では、大豆ミートを製造・販売する企業が増加し、多様な商品が市場に出回っています。
その中でも、味噌や大豆製品で名高いマルコメ株式会社の大豆ラボというブランドでは、多種多様なタイプの大豆ミートを展開しています。
- ミンチ、ブロック、フィレタイプ
- 保存が効く乾燥タイプや冷凍タイプ
- 大豆ミートを活用した調理品のレトルトタイプ
この多様なバリエーションのおかげで、ローストのような大きなブロック肉を使う料理以外はほぼ全て大豆ミートに置き換えることができるのです。
さらに、他のメーカーからも大豆ソーセージやハム、サラミなど多彩な商品が販売されており、その選択肢はますます広がっています。
大豆ミートのデメリット
環境や健康に良いとされる大豆ミートですが、果たしてデメリットは存在しないのでしょうか。
ここでは、大豆ミートに関する3つのデメリットについてお話しします。
動物由来のビタミンやミネラルが不足する

肉には重要な栄養素であるビタミンやミネラル、さらには皮膚や関節、筋肉、骨の生成に欠かせないコラーゲンが含まれています。
そのため、動物性食品を食べないベジタリアンは骨折のリスクが高まるとされています。
また、特に赤身肉に多く含まれる鉄分が不足することで、貧血が起こりやすい傾向があります。
「超加工食品」なので添加物が多い
本物の肉の食感や風味を再現するためには、多くの食品添加物が必要とされます。
例えば、食感を生み出すためにメチルセルロースが使用されていますが、動物実験では腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)が変化し、炎症を引き起こす可能性があるとの指摘があります。
また、肉の香りを出すための香料や、大腸がんのリスクが指摘されている亜硝酸塩を含む大豆タンパク質濃縮物が使用されている製品も多く存在します。
さらに、超加工食品は肥満・2型糖尿病・がんとの関連が指摘されており、摂取することで死亡リスクが増加する可能性があるとも考えられています。
値段が高い
大豆ミートの価格は、肉と同程度か、製品によっては肉よりも高価な場合もあります。
その背景には、国産大豆と輸入大豆の取引価格の高騰や、大豆ミートの流通量が食肉に比べてまだ少ないことが影響しているようです。
まとめ

ここまで大豆ミートに関する情報をお届けしてきました。
今後、ますます大豆ミートを食べる機会が増えることが予想されますが、デメリットを考慮すると、常食とするのは控えた方が良いかもしれませんね。
SDGsの概念が生まれるずっと前から、日本には豆腐や納豆、味噌など素晴らしい大豆由来の食品が存在していました。
大豆の植物性タンパク質や栄養素が美味しく楽しめる食文化を持つ日本は本当に恵まれていると感じます。
この機会に和食を再評価してみるのはいかがでしょうか。



コメント