今回は、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでよく見かける缶詰の中でも、多くの人々に親しまれている「ツナ缶」について、詳しくご紹介したいと思います。

このツナ缶は、非常に便利で、さまざまな料理にアレンジすることができる優れた食材として、多くの家庭で重宝されています。
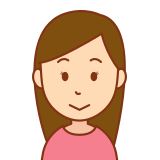
朝の慌ただしい時間帯に、手間をかけずに「さっと一品」を用意したい!!
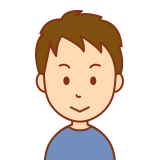
夜、疲れて帰ったときに、晩酌のお供に「何か一品」を作りたい!!
このようなシチュエーションで大いに役立つのが、使いやすさが際立つ「ツナ缶の魅力」です。
さて、皆さんは「ツナ」という言葉がどのような意味を持ち、どのようにして生まれたのかを知っていますか?
また、「シーチキン」も存在するけれど、何が違うの?同じものなの?」といった疑問を持ったことはありませんか?
最近では、さまざまな種類のツナ缶が市場に登場しており、「ノンオイル」や「ライトツナ」といった表記があると、その違いが分かりづらくなってしまうこともありますよね。
そこで今回は、購入後に後悔しないために、あなたが選ぶべきではない「選んではいけないツナ缶」を避けることができるよう、分かりやすくツナ缶の基本について解説していきたいと考えています。
ツナ缶のツナとはどのようなものか?
ツナ缶の「ツナ」という言葉は、英語の「Tuna」に由来しており、その意味は「マグロやカツオを含む魚の総称」を指しているのです。
実際、日本で販売されているツナ缶の原材料には、マグロだけでなくカツオが使用されているものも多く存在しています。
さらに、先ほど触れた「シーチキン」は、食品加工会社である「はごろもフーズが展開するツナ缶のブランド名」です。
つまり、ツナ缶とは「ツナ(マグロやカツオなどの魚)を主な原材料として作られた缶詰」であることを指します。
ツナ缶の賢い選び方
次に、ツナ缶の選び方について詳しく見ていきましょう。
ツナ缶を選ぶ際に考慮すべきポイントは、主に4つに整理できます。
- 使用されている魚の種類
- ツナ缶の加工方法
- 完成品の形状
- 販売時の包装形態
使用されている原料の魚
原材料となる魚の種類によって、ツナ缶の風味や味わいは大きく変わることがあります。
どのような魚が使われているかを一つ一つ確認することで、原材料ごとの特徴を理解していきましょう。
「ホワイトミート」または「ホワイトツナ」とも呼ばれ、身は白色であっさりとした味わいが特徴的です。
ツナ缶の原料としては古くから使用されており、その価格は比較的高価であるため、高級ツナ缶に利用されることが多いです。
料理に使うのはもちろん、そのまま食べても美味しさを堪能することができます。
これらの3種類の魚は「ライトツナ」と呼ばれ、びんながまぐろに比べて価格が安く、手頃な価格帯で販売されることが多いです。
きはだまぐろやめばちまぐろは、身が柔らかく、カツオに比べると脂が豊富で旨味も感じられます。
一方で、カツオはマグロを使用したツナ缶に比べて、身がしっかりしており、あっさりした味わいが多いという印象があります。
ツナ缶の加工方法
ツナ缶の加工方法は、主に3つの種類に分類されます。
その名の通り、「油に漬け込んで調理された」ツナ缶です。
油漬けにすることで、ツナ缶が持つ旨味を最大限に引き出すことが可能となります。
また、漬け込む油の種類によって、その味わいや価格も変わることがあるのです。
大豆油やサラダ油を使用したツナ缶は、一般的にリーズナブルな価格で提供されています。
一方で、オリーブオイルやアマニ油、えごま油などの高級な油を使用したツナ缶は、その分価格も高く設定されています。
しかし、高級な油を使用したツナ缶は、健康に良い成分が豊富に含まれていることが多いため、「体に良いものを選びたい!」と考えている方には、こういった商品をおすすめします。
「油と共にお水や野菜スープを組み合わせて調理された」ツナ缶です。
油だけで調理していないため、油漬けのツナ缶に比べるとさっぱりとした味わいが特徴となっています。
ただし、油を少なくした分、野菜スープを加えて旨味を増しているため、コクのあるあっさりとした味わいが生まれ、味のバランスが非常に良いツナ缶となっています。
「お水や野菜スープ、魚のエキスなどで調理された」ツナ缶です。
油を使用していないため、非常にヘルシーな商品で、カロリーを気にする方には水煮が特におすすめです。
さらに、調理の際に自分の好みに合わせて油を追加することで、油漬けと同様の調理も可能であり、「様々な調理法に利用できる」という点も魅力の一つです。
この3つ以外にも、調理の際に塩を使わない「食塩不使用」「食塩無添加」といった無塩タイプのツナ缶も存在し、こうした商品は「子どもの食事」や「介護食」として使いやすく、非常に人気があります。
完成品の形状
ツナ缶と言えば、多くの人がフレーク状のものを思い浮かべるかもしれませんが、実際にはツナの形状は3種類に分類されます。
最も一般的な形状で、ほぐす必要がないため「すぐに使いたい方」には非常におすすめです。
また、食べやすい形状のため、子ども向けの料理にも最適です。
フレークタイプよりも大きなサイズで、ゴロゴロとした一口サイズにほぐされています。
そのため、サラダやカレーの具材として「そのままの食感を楽しみたい方」にはこちらが非常におすすめです。
「ソリッドタイプ」や「ファンシータイプ」と呼ばれる形状で、身は一切ほぐされずにそのまま保存されています。
魚が輪切りにされた状態でそのままパッケージされているため、自分で大きさやほぐし具合を「アレンジして楽しみたい方」には最適と言えるでしょう。
さまざまな調理に応じて好みに合わせて使用できるため、料理の幅が広がります。
また、ツナ缶は身が大きな形状で含まれているほど価格も高くなるため、3つのタイプの中では「ブロックタイプ」が最も高価なものとなります。
「○○の時」はこのツナ缶がオススメ
ここからは、筆者が考える「シチュエーション別のおすすめツナ缶」をご紹介したいと思います。
「オリーブオイルやアマニ油、えごま油などを使用した油漬け」のツナ缶が最適です。
健康に良いとされる油を使用して製造されたツナ缶は、料理に利用することで栄養をしっかりと吸収することができるため、非常におすすめです。
離乳食などに最適なのは「水煮や食塩不使用のフレークタイプ」のツナ缶です。
味付けが薄く、調整がしやすいため非常に使いやすいです。離乳食だけでなく、小さなお子さんの食事にも適しており、子どもたちがツナマヨを好む理由もここにあります。
ツナ缶の旨味が最大限に引き出されている「油漬けのブロックまたはチャンクタイプ」のツナ缶が最適です。
自分好みにほぐしながら味わうことができるので、非常におすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?

ツナ缶の種類や加工方法によって、風味や味わいは多様に変化しますので、ぜひこの機会に自分にぴったりな商品を見つけていただければと思います。
最後までお読みいただき、心より感謝申し上げます!!







コメント