死亡保険や医療保険、学資保険、さらには個人年金保険など、私たちの人生において直面しがちなさまざまなリスクに備えるために、多くの生命保険会社が多様な保険商品を展開しており、そのラインナップは非常に豊富です。
がんにかかってしまった場合には、果たしてどの程度の費用が発生するのか、また小さな子供がいる家庭において、万が一のことが起こった場合に残される家族はどのような影響を受けるのかという不安を抱いている方は少なくないでしょう。

このような不安から、多くの方が「生命保険に加入するべきだ」と考えるのは自然なことです。しかし、その前に、もしもの事態が発生した際に、国からどのくらいの補償が得られるのかを知っていますか?
民間の生命保険に加入する前に、まずは国の社会保険制度について十分な理解を深めておくことが非常に重要です。
社会保険とは
社会保険とは、私たちの生活を支えるために、死亡や病気、老後に備える目的で国が設けた保険制度のことを指します。この制度は様々なカテゴリーから成り立っているため、理解が難しい部分も多いのですが、それぞれの制度について詳しく解説していきます。
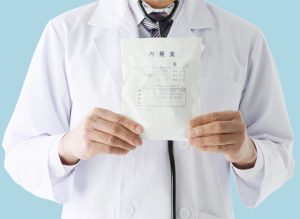
①医療保険
医療保険によって、病院での医療費負担は基本的に3割となります。特に75歳以上の方の場合は、原則として1割の負担で医療サービスを受けることが可能です。また、出産時に受け取ることのできる一時金や、高額療養費制度といった補助的なサポートも存在します。
②労働保険
労働保険には、雇用保険が含まれており、これは失業や育児、介護を理由に休職中の方や職業訓練を受ける際に給付金が支給される制度です。
さらに、労災保険は、業務中や通勤途中の事故、あるいは業務によって引き起こされた病気に対して、労働者やその遺族に対して補償を行う制度となっています。
③介護保険
将来的に介護が必要となった場合には、介護保険サービスを利用できる仕組みが整っています。介護サービス事業者に対して、所得に応じた1~3割の自己負担金を支払うことで、必要なサービスを受けることができます。
④年金保険
年金保険は、いわゆる老後に受け取ることのできる年金に関する制度です。老齢年金は自分の老後の生活費として受け取るものであり、障害認定を受けて働けなくなった場合には障害年金が、万が一亡くなった場合には遺族年金が家族に支給される仕組みとなっています。
このように、社会保険制度は相互扶助の理念に基づいており、どんな状況で誰が遭遇するか分からない「万が一」に備えるために、お互いに資金を出し合って助け合う仕組みです。この制度は、国民からの保険料だけでなく、税金を含むさまざまな資金によって支えられています。
万が一の時、どれくらい補償が受けられる?
では、具体的にどのような状況において、どの程度の補償が得られるのかを確認してみましょう。

大きな病気になった場合
もしも大きな病気にかかり、入院や手術が必要になった場合に、実際にはどのくらいの費用がかかるのでしょうか?
まず、社会保険のおかげで、病院での医療費は基本的に3割負担となります。しかし、3割という負担額であっても、入院期間が長引いたり、大規模な手術が行われると、実際の医療費が想定を超えることがあります。
その際に役立つのが、高額療養費制度です。この制度は、同じ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、定められた限度額を超えた分について払い戻しが受けられる仕組みです。
自己負担の限度額は年齢や所得によって異なりますが、一般的な世帯主の年収であれば、自己負担額はおおよそ8~9万円程度となることが多いです。
ただし、病院での支払いには医療費だけでなく、食事代や差額ベッド代なども含まれるため、実際には完全に8~9万円以下には収まりません。
一家の大黒柱が亡くなってしまった場合
例えば、会社員の夫が、妻と幼い2人の子供を残して突然亡くなったと仮定しましょう。このような事態は、考えたくもないものですが、万が一は誰にでも起こり得ることです。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類が存在します。自営業の方が亡くなった場合は遺族基礎年金のみが支給される一方、会社員だった場合には遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金も受け取ることが可能です。
遺族基礎年金の金額は、主に残された家族の構成によって定まります。遺族厚生年金は、主に会社員として働いた年数やその期間の収入によって異なります。
具体的には、遺族基礎年金は年間777,800円に加え、子供の数に応じた加算が行われます。子供1人目と2人目にはそれぞれ223,800円、3人目以降は1人あたり74,600円が加算されることになります(2022年4月からの金額)。
遺族厚生年金は、亡くなった夫が会社員として働いていた期間とその収入に基づいて変動しますが、平均的には約500,000円と考えられています。
このケースにおいて、妻と2人の子供がいる場合、子供が18歳になるまでに受け取る遺族年金の総額は約1,725,400円に達することになります。
その後は、妻の収入によって変わることになりますが、ひとり親家庭向けの児童扶養手当も支給されることになります。
さらに、夫名義の住宅ローンが残っている場合でも、団体信用生命保険により、住宅ローンは完済される仕組みとなっています。
まとめ
このように、日本の社会保険制度は非常に充実しています。万が一の際に、国からこれだけの補償を受けられることを理解することが非常に重要です。
国からの補償だけで十分だと感じる方は、民間の生命保険に加入する必要がないかもしれません。しかし、自営業の方などは労働保険や厚生年金を受給できない場合もあるため、その不足分を補うために民間の生命保険に加入することが必要とされるケースもあります。
私自身、このような記事を執筆している際に、実は民間の生命保険に大きな魅力を感じています。
会社員でありながら、しっかりと生命保険に加入し、自分自身や家族が万が一の際に安心できるよう備えています。なぜなら、もし自分や家族が大きな病気にかかってしまった場合、金銭的な心配をせずに安心して治療を受けることができると考えているからです。それこそが、私にとって非常に重要な安心を得るための方法だと思っています。
国の社会保険について知らずに民間の生命保険に加入することはお勧めできません。国からの補償を理解した上で、自分に必要だと感じる生命保険に加入することを推奨します。あなたにとって最適な生命保険が見つかることを心より願っています。




コメント