
「株主優待」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょうか?
テレビ番組やインターネットの記事において、「株主優待を利用して日常生活を楽しんでいる方へのインタビュー」などの形で紹介されることがしばしばあります。
しかし、実際には「株式投資についてはまったくの無知」という人や、「株主優待株とは一体何を指すのか?」と疑問を抱いている方々がたくさんいるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、株式投資や株主優待に興味を持っている方々に向けて、基礎知識から実際の運用方法まで幅広く解説していきます。
株式・株式投資とは
企業が事業活動を行うために資金を調達する手段の一つに「株式発行」があります。
ここでいう「株式」とは、企業がこの目的で発行する証券のことを指します。
株式を購入した人は「株主」と呼ばれ、企業の資金提供者の一員としての地位を得るのです。
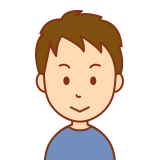
会社を設立するためには500万円の資金が必要です。
しかし、そんな大金を手元に持っているわけではありません。
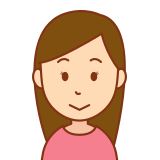
その場合、株式を発行して資金を集めるのが良い手段です。
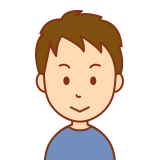
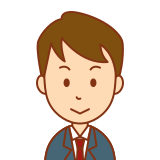
私に200株を購入させてください。
その代わり、私は会社の株主となります。
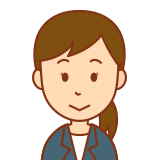
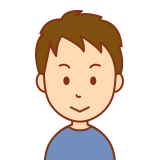
ありがとうございます。
これで事業資金が確保できましたね!
株主は、企業に対して資金を提供することの対価として、株主総会での議決権や配当金、そして株主優待を受け取る権利を持つことができます。
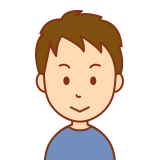
今年、我々の会社は100万円の利益を上げました。
株主の皆さんには、一株あたり1000円の配当金をお返しします。
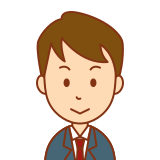
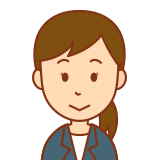
このように、企業は資金を得ることができ、株主はその出資に対する対価を受け取ることができます。
実際には、このようにスムーズに進行することは稀ですが、大まかな流れとしてはこのような形になります。
株式投資のメリット・デメリット
それでは、株式投資を行うことによって得られるメリットとデメリットにはどのようなものが存在するのでしょうか?
メリット
デメリット
株主優待株とは
株主優待株とは、株主に対して還元を株主優待品と称される金券や商品を通じて行っている企業の株のことを指します。
企業が定めた株数の株式を「権利確定日」の時点で保有していることが条件となり、その株主優待品が企業から送付される仕組みになっています。
また、権利確定日までに株式を保有するためには、最低でも2営業日前の「権利付き最終日」までに株式を購入する必要があります。
株主優待として一般的に提供される商品には、以下のようなものが含まれます。
- 米・飲料
- 自社製品
- 金券・クオカード
- カタログギフト
- その他
このように、株主優待は非常に実用的で価値のある商品が多いため、株式投資を始めたばかりの方や主婦層にとても人気があります。
また、これら以外にもユニークな株主優待品を提供している企業が多数存在するため、興味のある方はぜひ調べてみると良いでしょう。
株主優待株を始めるメリット・デメリット

株主優待株を始めることには、いくつかの明確なメリットとデメリットがあります。
メリット
デメリット
買ってはいけない株主優待株とは

ここまでの内容を踏まえると、株主優待株は非常に人気があり、値下がりしにくく、継続的なメリットを享受できる可能性が高いと思われがちです。
しかし、株主優待株には注意すべき落とし穴が存在します。
それは、業績が悪化したり、有事の際に非常に脆弱な株が存在するという点です。
人気の株主優待株は、多くの株主優待目的で投資をする個人投資家によって株価が下支えされています。そのため、有事や業績の悪化が発生すると企業が優待を改悪または廃止せざるを得なくなる場合があり、そうなれば個人投資家による株価の下支えを失ってしまいます。
その結果、他の株式と比較しても著しい大暴落が発生するリスクがあるのです。実際に、2020年に発生した新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、優待を廃止した企業では株価が大きく下落しました。
また、優待による人気が原因で株価が不当に高くなっている株も存在するため、そのような株も優待の廃止による暴落リスクが非常に高いことに留意が必要です。
これらのリスクを回避するためには、以下の点に注意して株主優待株を購入することが重要です。
- 同じ業種や企業に過度に集中して投資することを避ける(分散投資を行うこと)。
- 自己資本比率を確認する。
- 利回りが極端に高い株には慎重になる。(経営を圧迫している可能性があるため)。
自己資本比率とは、企業の倒産リスクを評価するための指標の一つで、一般的には30%以上が安全圏とされています。
また、配当金に加えた総合利回り(配当利回り+優待利回り)が過度に高い場合は、株主への還元が企業経営を圧迫している可能性があるため、そのような株への投資は避けるべきです。
まとめ
株主優待株は、その人気と魅力によって株価が下支えされている一方で、大きな落とし穴も存在することが理解できたのではないでしょうか?
十分な資金があれば、さまざまな株式に分散投資を行い、リスクを軽減することが可能ですが、まとまった資金がない方は、1株からの投資を通じて分散投資を始めることも一つの選択肢です(分散投資にはインデックス投資なども含まれます)。
株式投資の世界には、株主優待株以外にも高配当株やグロース株、外国株、ETFなど多様な選択肢が用意されています。優待株だけでなく、他の投資スタイルにも目を向け、「投資生活」を存分に楽しんでいただけることを心より願っております。
本記事はここで締めくくります。ご覧いただき、心より感謝申し上げます。

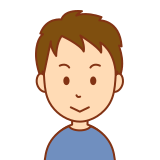


コメント