冠婚葬祭のマナーに関して、悩んだ経験を持つ方は多いのではないでしょうか。さまざまな伝統や一般常識が求められる場面に遭遇することもあるでしょう。
昭和時代には、大家族の中で祖父母から多くの知恵を学ぶ機会が豊富にありました。しかし、近年では核家族化が進行し、少子化の影響も伴って、昔ながらの知恵や人との付き合い方、マナーを学ぶ機会が急激に減少しています。
さらに、冠婚葬祭は頻繁に行われるわけではないため、覚えておくべきことが少なくなり、私自身も、相手に失礼がないようにと調べることが頻繁にあります。調査には手間がかかり、時には面倒だと感じることもあるかもしれません。
そこで、今回は以下のポイントについて詳しく解説します。
・ お供えにふさわしくない商品とその理由
・ 迷った際のおすすめのアイテム

お供え物として、どのようなものがあるのでしょうか?
| お花(供花) | アレンジメントフラワーやスタンドフラワー、花輪など多様な選択肢があります。単体で飾る際は「ひとつは1基、ふたつは1対」と表現し、価格帯は7,000円から30,000円と幅広いです。 |
| お供えもの(供物) | 香やろうそく、果物やお菓子などが一般的です。進物用としては5,000円から12,000円が相場となっています。 |
| 弔慰金(香典) | 白と黒の水引の不祝儀袋に包む必要があります。近隣の方には3,000円から5,000円、会社関係者や知人には5,000円から1万円程度が一般的な金額です。 |
どんな時にお供え物が必要なのでしょうか?

マナーについての豆知識<覚えておくと便利>
書き方・入れ方・準備の仕方に関するポイントです。
- のしを付ける際には、表書きは水引の上に目的用途を記載し、その下には送り主の氏名を書くのが基本です。
- 氏名は目的よりも少し小さく書くのが一般的です。
- 表書きにはボールペンや万年筆は使用しないようにしましょう。
- 毛筆を使用し、慶事には濃く、弔事には薄く楷書体で書くことが望ましいです。

- お札を入れる中袋には金額を記載します。慶事の場合は表に、弔事の場合は裏に「金〇阡円・金〇萬円」と書き、共に裏側には住所と名前を記入します。
- 弔事についても慶事と同様に書いても問題ありません。
- 数字の中で、4(死)、6(無・亡)、9(苦)などは避けて金額を設定しましょう。
- お札は新札を避けることが一般的です。新札の場合は折り目を付けて入れることが望ましいです。
- お札の入れ方は、慶事の場合はお札の顔が表に、弔事の場合は裏に来るように入れます。
- 封はしないで、包みの折り方は悲しみを流すため、上側を下にかぶせる形にします。
お供えで購入してはいけない商品とその理由
お花としては、赤いバラや彼岸花が避けるべきものです。これらは華やかさを持つ花であることや、棘や毒を持つもの、さらには人を傷つける可能性のあるものだからです。仏様の国は清らかなお浄土であるため、香りが強すぎるものも避けるべきです。
ただし、故人が好きだった花で、かつ家族の了承が得られれた場合は送ることが許されます。
淡い色合いや白の大輪の胡蝶蘭の鉢植えは、お祝いの印であるため、避けるべきです。また、鉢植え自体を飾ることを好まない方もいるため、無難に避けるのが賢明です。
お供え物としては、肉や魚など、殺生を連想させるものは避けるべきです。これは、精進料理の考えに基づき、仏教では本来殺生を禁じているためです。加工品であっても、避けるのが賢明です。
造花や電子ローソクは手間がかからず便利ですが、できるだけ生花と火を灯すことをおすすめします。火の扱いが危険な年齢で無理な場合は、安全な電子ローソクを利用するのが良いでしょう。
迷った時のおすすめの品々
仏式の場合の決まり事として、仏教のお供えには「五供」と呼ばれる、仏前にお供えするのに適したものがあります。これらは故人があの世で役立つものと考えられています。
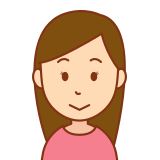
お花(供花)のポイント
| お花 | 初七日まで 葬儀と同日が多い | 白一色の花(白菊・白ユリなど)を送ることが一般的です。通夜告別式は葬儀場を確認してから手配することが望ましいです。 |
| 初七日~ 四十九日まで | 白い花でまとめることが多く、「白上がり」と呼ばれます。少し寂しくならないように、淡いブルーや紫の花を差し色として入れることも可能です。 | |
| 節目一周忌~ 七回忌くらいまで | 故人が好きだった花や、少し明るい色合いの花を選ぶことも可能ですが、派手になりすぎないように注意が必要です。淡いピンクや黄色が適しています。自宅に節目などで送ることもあります。 |
時が経つにつれて、白から徐々に淡い色合いが増えていくのが望ましいとされています。
お供え物(供物)の種類やおすすめ商品
| お供え物 | 果物 | 地元の名産や季節のもので、傷みにくいものが適しています。リンゴやメロン、みかんが日持ちするため、定番の選択肢です。 |
| お菓子 | 常温保存ができ、日持ちするもの。小袋や個包装になっているものが好まれ、後で振る舞えるように用意します。 | |
| 水(飲料) | できるだけ清潔な状態のものが望ましいです。お茶も選択肢の一つです。 | |
| 灯明 | ろうそくを使用します。火の光は神聖なものとされ、場所を照らす道しるべとしての役割を果たします。 | |
| 香り(線香) | 間違いなくおすすめの品です。清める意味や、綺麗にする意義があります。 |
- 楽天市場→楽天 味噌煎餅 日持ちもしており、お試し商品もあるためおすすめです。
- 楽天市場→カラフルバームクーヘン詰め合わせ 使用後は小物入れとしても活用でき、引き出しボックスとしても利用できます。色を抑えた箱は線香やろうそく入れとしても使えます。
- 楽天市場→線香ギフト 線香セット 微煙タイプで、高級感のある筒に入ったギフトで、贈り物に最適です。
まだまだおすすめ商品はたくさんありますので、ぜひ検索してみてください👉 楽天市場

お供え物《マナー編》購入してはいけない品のまとめ
お花の中ではバラや彼岸花が、お供え物として購入してはいけないものです。彼岸花は意外な選択肢ですが、その名前だけでは判断が難しいかもしれませんね。
このように見ていくと、なるほどと思うことが多くあります。何よりも大切なのは、先祖や故人を思いながらお供えを選ぶことです。
生ものに肉や魚、傷みやすいものは避けることが基本です。

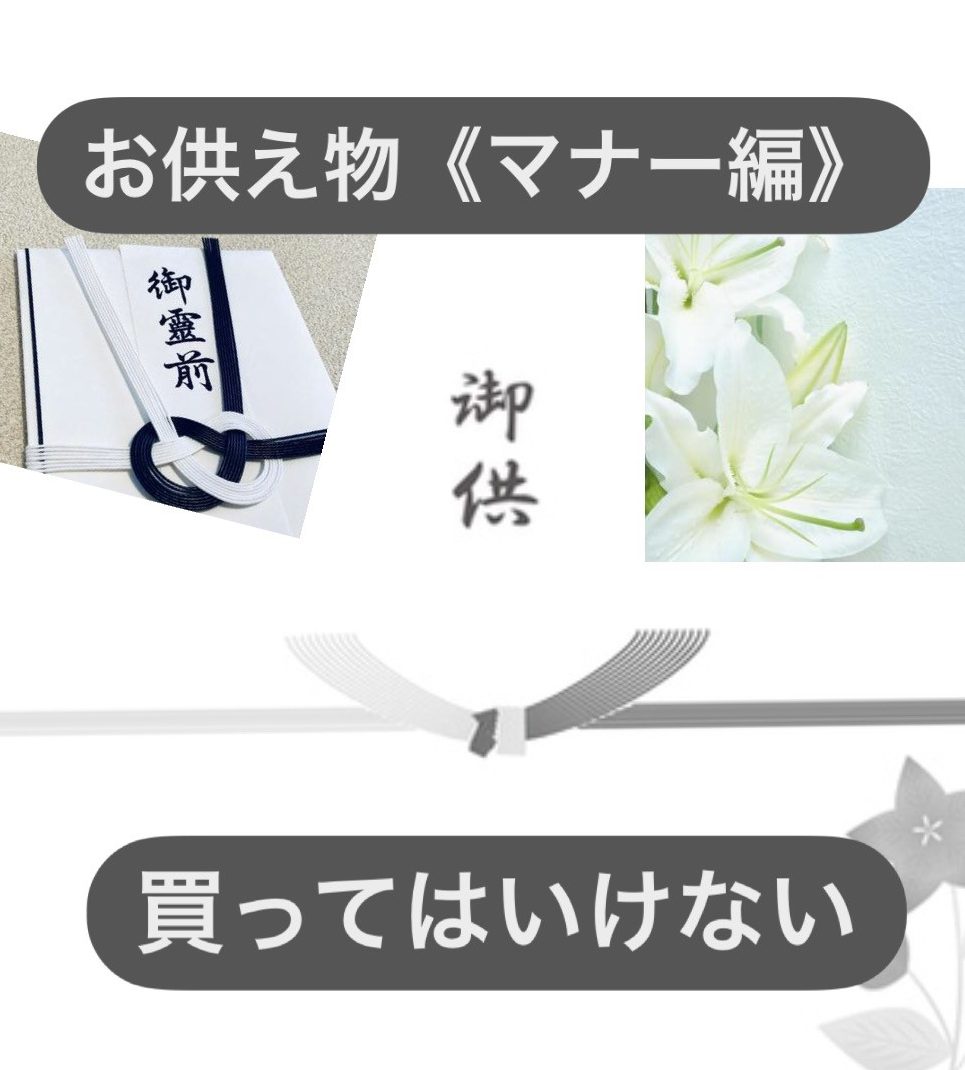


コメント